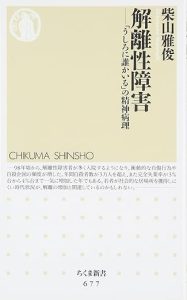俺が長年興味を持ってきたものに『夢』と『世界観』がある。前者は寝ているときに見る夢のことで、後者は説明が難しいのだが場所や景色を取り巻く言語化できない感覚を指していて、雰囲気、ムード、空気感などと言い換えることもできる。その二つに加えて『夢の中にしか存在しない世界観』というのもあり、これは文字通り現実世界のどんな場所に行っても感じられない、夢の中だけに存在する場所でしか感じられない雰囲気のことだ。そう聞いてなんとなく想像がつく人もいれば、なんのことが全くわからないという人もいると思う。夢の中にしか存在しない世界観は、人間の根本的な機能である『自我』や、果てはこの世界(物質世界・精神世界)の仕組みにまで関係すると俺は思っているのだが、このことについて語っている人をほとんど見たことがないので俺が書いてみようと思った。
この記事では夢の中にしか存在しない世界観について、中学の頃に試していた明晰夢・体外離脱体験や20代後半のときの幻覚剤体験(事故含む)などを踏まえ、自我や記憶、昨今のAI生成画像などの要素に分解して、現時点までで気づいたことを書いていく。他に書く場所がないので、死やシミュレーション仮説についても触れる。夢の中にしか存在しない世界観について体感があるかどうかはその人の経験、感受性、脳の機能などにほとんど依存していると思うが、興味があればこの記事を読んでみてほしい。約3万文字あるが文献や論文はほとんど参考にせず俺の体験と独自理論で構成されているのでご了承ください。
世界観とは
夢の中にしか存在しない世界観についていきなり説明しても多くの人はピンとこないと思うので『世界観』と『夢』に要素を分解して説明していく。結局はどちらも体感がすべてなので、文章を通じてどれだけ伝えられるかはわからない。夢の世界に興味を持って夢日記をつけていたり、人生が辛くて現実より夢の世界がメインになったような経験がある人や、明晰夢や体外離脱の練習をしたことがある人には伝わりやすいかもしれない。
まず俺が言う『世界観』という概念についてだが、冒頭に書いたように雰囲気やムードや空気感とも言い換えることができる(この記事では文脈に応じてそれらの言い方を使い分けている、または表記揺れしているがすべて同じ概念を指している。主に現実に関することには雰囲気、夢に関することには世界観という言葉を使っている)。場所、物、人、時代、時期、状況、匂い、映画、小説、音楽など、この世に存在するものはすべてそれぞれの世界観・雰囲気を持っている。例えば小学生の頃にしか感じられなかった雰囲気や、人生のある時期にしか感じられなかった雰囲気など、人は常に何らかの雰囲気を感じながら生きているはずだ。自分の部屋でも雨の日や晴れの日、季節によっても感じられる雰囲気が違うし、模様替えをしたり家具の配置を変えるだけでも雰囲気は少し変わる。誰と一緒にそこにいるかによっても違うし、外出して部屋に帰ってみるとまた違って感じる(どこに行ってきたかも影響する)。そう考えると世界観・雰囲気というのは単純に『気分』とも言えるかもしれない。だから何、当たり前じゃないの?と思うかもしれないが、俺はこの概念が無性に気になり、小学校低学年の頃から今に至るまでずっと考えている。
人間(他人)もそれぞれ世界観を持っていて、例えば知り合いをランダムに一人思い浮かべて見ると、その人を想起したときにしか感じられない雰囲気がないだろうか。それはその人の住んでいる場所、性格、職業、現在の状況、その人の周りの人間関係などの細かな情報が入り混じって発生しているのかもしれない。
フィクションの作品にも世界観があり、例えばアニメ、ドラマ、映画も90年代、00年代、10年代と年代によって全体的な雰囲気が違うし、国によっても違い、挙げだすときりがない。もちろん作品によって一つ一つ世界観があり、その作品に触れた人はそれを感じることになる。音楽は聴覚と言語の2つで構成されていて、小説、本、もしくはブログ記事やツイートは言語のみで構成されているが、それでも世界観を感じられる。
またフィクションの作品は、その作品に触れると自分の人生のある時期を思い出す、ということがある。よく言われる、ある音楽を聴くと青春時代を思い出す、とかそういうものだ。思い出すと言っても『その頃のエピソードを言葉で淡々と思い出す』というレベルの想起と『実際にその頃の自分の状態に戻ったように、体感として感覚や感情が蘇る』なのか、度合いがあるはずだ。俺が言う世界観・雰囲気を感じるというのは後者の状態を指す。それはフラッシュバック的で、ネガティブな記憶の場合パニックを起こすほどリアルな場合がある。例えば『匂い(嗅覚情報)』はもっとも顕著に、体感として世界観・雰囲気をフラッシュバックさせる。
以上が俺が言う世界観の概観で、以下に匂いとフラッシュバックの関係について書く。
匂いとフラッシュバック
ふとしたときに懐かしい匂いを嗅いで、人生のある時期を強烈に思い出した、という体験はないだろうか。俺はそういったことがそこそこの頻度で起こるが、匂いによって呼び起こされる記憶は形だけのエピソード記憶とは違い『一瞬、本当にその頃の自分に戻った』ような体感がある。俺の場合それと同時に、その頃の自分と現在の自分を対比して、自分がいかに変化したかを痛感したりする。
具体的なエピソードとしては、神社仏閣を訪れて室内に入ったときに線香の匂いを嗅いで実家の神棚を思い出し、そこから芋づる式に小学生の頃を思い出したり、むかしよく作っていた料理(ごま油と鉄鍋で作るチャーハン)を久々に作って、調理時の匂いでその頃を思い出したりした。2023年の暮れ、仕事が終わって駅で帰りの電車を待っている時、人混みの中の誰かから俺が10代後半の頃に使っていた8×4の制汗スプレーの匂いがして、ほんの数十秒だけその頃の自分に戻ったような体感があったりした。また近年の旅行で小学生ぶりに銭湯に入った時、小学生の頃の感覚が銭湯に入っている間中ずっと呼び起こされていた。また俺は小学生の頃から、秋口に部屋の窓をあけて冬の匂いがすると小学生なりに過去のことを思い出して寂しくなったりしていた。これらはPTSDによるものよりは弱いと思うが一応『フラッシュバック』と呼んでもいいのではないかと思っている。
このようなことが起こるのは、匂いを感じる脳の部分と、記憶を司る脳の部分が物理的に近いからだそうだ。他の五感で言うと、懐かしい音楽や懐かしい映像などもそこそこ記憶を呼び起こすが、体感まではいかないことが多い。懐かしい味などは嗅覚の次くらいに記憶を呼び起こす気がする。触覚に関してはあまりピンとこない。いずれにしても、音楽や映画などで感動したときに鳥肌が立つ人と立たない人がいるように、懐かしい匂いを嗅いでも特に何も感じない、という人もいるのだろう。世界感を感じるのは感覚的、無意識的、直感的であり、感じまいとしても感じてしまうものだ。
以下では『人生の各記憶』が持つ世界観について書いていく。
人生の各時期の世界観
上に小学生の頃にしか感じられなかった雰囲気や、人生のある時期にしか感じられなかった雰囲気などと書いたように、自分の記憶を遡ってみると人生の各時期によって感じられる雰囲気が違うはずだ。少なくとも俺はそうなのだが、すべての人間がそうかはわからない。生まれてからずっと一本調子で、幼少期も大人になってからも何の雰囲気の違いも感じないという人もいるかもしれないが、俺の脳はそうなっていないので、そういう人の感覚を理解することは出来ない。
俺は自分の人生をざっと思い出すと、大きく分けて幼稚園の頃、小学校低学年・中学年・高学年、中学生、高校生、20歳前後、名古屋に引っ越した24歳の頃、幻覚剤事故を起こした26歳の頃(2019年)、コロナ禍、名古屋から別の場所に引っ越した30歳の頃(2023年)など、各時期・フェイズがあり、それぞれの時期で感じられる雰囲気は違い、26歳の頃と30歳の頃は雰囲気が同じだった、などということはない。当然、中1の冬や23歳の秋、など各時期をさらに細かく分けることもでき、思い出したときに感じられる雰囲気もより鮮明になる。特に印象的な出来事があった場合は、ある一日、という風に日単位・シーン単位で記憶されている場合もある。これは珍しいことではなく多くの人がそうだと思う。
この記事を読んでいる人も自分の人生の印象的な時期を思い出して雰囲気を感じてみてほしい。または多くの人に共通の強烈な時期であるコロナ禍を思い出してみてほしい。コロナ禍のとき特有の雰囲気がなかっただろうか。もちろんコロナ一年目、二年目、など細かな時期によっても雰囲気は違う。ただし今頭がはっきり覚醒している場合、形としてエピソードは思い出せても雰囲気・体感はありありと想起できないかもしれない。それは『自我』という機能が良くも悪くもうまく働いているからだと俺は思う。本当にありありと雰囲気を体感するには、自我の機能を停止させたり、その時期の夢を見たり、匂いを感じたり、という条件が必要なのだが、それらについて詳しくは後述する。
人生の各時期の雰囲気が変化するターニングポイントについてだが、多くの場合この日を境に人生の雰囲気が変化した、という明確なターニングポイントはないものと思われる。人生の状況や環境の変化が大きいほど、または感情が強く動いた時期ほど、記憶も雰囲気も強烈に残るということは間違いない。
基本的には歳を取るほど状況の変化も感情の動きも少なくなり、雰囲気が変化するスパンが長くなる。よく言われるように、思春期である10代の頃は環境も状況も感情も変化が大きく、変化が訪れるスパンが短いので、10代の頃というのは強烈に濃い期間になるように思う。小6の1学期と3学期では全く違うし、中1と中3でも全く違うということが多いはずだ。実際に自分の人生を思い出してみても10代の頃は雰囲気の変化が多く、現在に近い時期ほど雰囲気の変化のスパンが長くなっている。俺は現在30歳を過ぎていて、2024年の春から在宅で働いていて同じような日々の繰り返しというのもあり、2024年春から2025年3月現在まで大きな雰囲気の違いを感じない。2024年を思い出しても2023年を思い出しても、想起される雰囲気に大きな違いがない。若い頃の記憶を思い出すと、人生が次のステージや章に移行していっているような印象を受けるが、最近はあまりそのようなダイナミックさを感じにくい。
誰しも今現在感じている雰囲気が最新だが、未来になって現在を回想してみたときにどのように感じるかはわからない。また自分が今後どのような雰囲気を持つ日々を生きることになるかもわからない。少なくとも俺の場合人生の各時期が持つ雰囲気はそれぞれ固有であり、例えば中2の冬と25歳の冬は鬱屈としていたという点で雰囲気が似ているが、同じということはない。なので例えば、35歳になってまた24歳の頃のような雰囲気の日々になってきた、ということはないと思われる。というより俺は昔から、そういったことになると想像すると自分だけが世界に取り残されたような気分になり恐ろしいと感じる。例えば俺は2015年くらいまでのインターネットが好きで、今でもWindows XPやMSNメッセンジャーを使っていた日々を思い出して懐かしくなるが、またその日々に戻ると思うと恐ろしいと感じる。本題から逸れるので詳しくは割愛するが人はどのような世界観・雰囲気を持つ未来に行きたいかをリアルにイメージすることで、望む未来・世界をある程度引き寄せることができると俺は思っている。同じような雰囲気を二度と繰り返したくないと思っている限り、実際に繰り返すことはないんじゃないだろうか。
俺が気になるのは、なぜこんなにも各時期で雰囲気が違うのか、雰囲気というものを作っているのはなんなのか、ということだ。おそらく、その時の状況、やっていたこと、関わっていた人、触れていた作品、食べていたもの、部屋の状態、世界の状況など自分を取り巻くあらゆる状況、そして脳そのものの変化(思春期や老化)などが関係しそうだ。それらを一言でまとめると『情報』であり、厳密に言うと『自我の構成』の情報が関係するのではないかと思っている。
上述の匂いによって呼び起こされる『体感としての記憶』が、夢の中にしか存在しない世界観を語る上でも重要になる。俺は匂いは各時期の『自我の構成』を呼び起こすと考えた。もしくは『自我の機能(膜やフィルター的だと俺は思う)』や『潜在意識と顕在意識の境界線』が弱い人が世界観を感じやすく、また匂いなどを通じてフラッシュバックを起こしやすいのではないだろうか。以下に、自我という機能について書き、俺が言う世界観という概念についてまとめる。
仮説1:自我の構成が世界観を作る
先程の『世界観を作っているのはなんなのか』ということの仮説として『自我を構成する情報』が作っているというものがある。自我(エゴ)と聞いて「わがままのこと?」と思う人はそもそもこの記事を読むことに向いていないと思う。俺もフロイトやユングを専門的に勉強したわけじゃないので正確な定義はわからないが、俺が定義する自我の機能は大きく分けて2つある。
俺が思う自我の1つ目の機能は、主に人格に関係する情報の構成で主に『自分はこういう人間だという情報(名前、住所、職業、経歴、記憶、好き嫌いなど)』や『思考パターン』の2つだ。要は自分にまつわる膨大なデータベースのようなものだ。俺はそれらは一言でいうと『優先順位』ではないかと思っている。この世に生きている限り一瞬一瞬必ず何かを選択せねばならず、何もしないということすら、何もしないという選択となる。その選択を決めるのは自我であり、自我に書き込まれた何を優先するかという基準に従っている。俺はこのことを考える時、FF12のガンビットという戦闘システムを思い出す。ガンビットとは戦闘中に設定したある条件にあてはまった時に仲間キャラクターが自動で行動するための設定で、例えば『味方のHPが30%になったらケアル>味方が毒状態になったらポイゾナ>火に弱い敵にファイア』という風に優先順位が要となっている。ここまでシンプルではないが、すべての人間の自我もガンビットのようなもので、現在設定された優先順位通りに無意識に選択を行っているのではないかと思う。
自我の構成は毎日少しずつ変化している。人間は一日8万回思考をするらしく、日々何かを経験し、考え、という繰り返しの中で小さなことから大きなことまで、何を優先するかという基準が少しずつ変化している。何年も経つと文字通り別人のように優先順位が変わっている場合もあるだろう。世界観に関する一つの仮説としては、その『優先順位・並び順』及び『構成状態』がその時期特有の雰囲気を作っているのではないかということだ。
仮説2:自我のフィルター機能が弱いと世界観を感じやすくなる
俺が思う自我の2つ目の機能は、自我とはこの世界を認識するための知覚そのもので、時間の感覚さえも制御していると俺は思っている。今普通に目が覚めていて、幻覚が見えることもなく、人格、思考、記憶に一貫性があり、自分を自分だとちゃんと認識できる、というなら自我がちゃんと機能している証拠だ。
『体感時間が他の人と比べて大きく違っていない』
『自分の過去がちゃんと存在したと思える、自分の過去を自分の過去だとちゃんと確信できる』
という当たり前のことも、自我の機能によるものだ。
逆に『幻覚が見える、幻聴が聞こえる(統合失調症)』『離人感がある(離人症)』『人格が複数あり、切り替わることがある(解離性同一性障害)』『何かをきっかけに現実から意識が解離する(解離性障害)』『ふとしたきっかけでフラッシュバックが起こる』など、目が覚めている状態でそのような知覚になる場合は、自我がちゃんと機能していないということだと思う。
俺がそう思うのは、2019年10月にアカシア茶及びアヤワスカアナログと呼ばれるDMTという種類の幻覚剤を服用してトリップし、視界が変容し、閉眼幻覚が見え、BADに入り『自分の過去を自分の過去と思えない』などの精神状態になったり、2023年3月にCBDだと言われて合成カンナビノイド(THCo+HHCo)を渡され10パフして『10秒が1分に引き伸ばされる』などの体験をしたからだ。幻覚剤は自我を崩壊させることで日常では体験できない異常な知覚を引き起こすと言われている。
解離性障害や統合失調症も『自我障害』とくくられているようだ。それらの障害は自我及び『自分を統合するもの』が機能不全を起こしている状態であり、例えるならビーズのネックレスの紐の部分や串団子の串の部分がそれにあたるのではないかと俺は考えた。ネックレスの紐が抜けるとビーズはばらばらになり、串団子の串の部分が抜けると団子がばらばらになってしまう。解離性障害と統合失調症は症状が似通っていて診断が難しいらしいが、両方とも根本は自我及び『自分を統合するものが失調している』ということなんだろう。
自我の『世界を知覚するための機能』や『自分を統合する機能』は『フィルター』や『膜』のようなものにも例えられると俺は思っている。なぜフィルターなのかと言うと、人間が一個人としてこの世界に生きるには『自分』と『外界(他者)』の間にある程度境界線を作る必要があるからだ。フィルターが薄いと、良いものも悪いもの問わず世界からの情報をダイレクトに受け取ってしまい、奥まで入り込んだりして様々な不都合が発生する。
例えば俺は幼稚園や小学生の頃、その日見た映画の世界観や余韻を翌日まで引きずっていた。映画に没頭し観終わると映画ロスのようなものが発生するが、自我のフィルター機能が弱いと内容が自分の奥深くまで入り込みすぎるのか、その世界観が抜けるまで時間がかかる。あまりの喪失感で学校に行くのがいやになったこともある。小学校1年生の頃にニンテンドー64でマリオストーリーをクリアして、ゲームロスがひどく何日間か引きずったのも覚えている。そういった傾向は歳を重ねる事に減ってきて、今はそういった余韻は数時間で消えるようになった。
上述の、匂いで記憶がフラッシュバックするのも自我のフィルターが薄いせいではないかと思う。この場合は『潜在意識と顕在意識の間の境界線のようなものが薄い』と感じる。記憶とは潜在意識の奥深くに封印されていて、基本的には日常の中でいきなり感情・体感を伴って思い出す(フラッシュバックする)ことはない。しかし自我のフィルター及び潜在意識と顕在意識の境界線が薄いとそれが起こる。例えば俺のように匂いによって軽いフラッシュバックが起こるのもそうだし、俺が今まで出会ったある解離性障害の人の中には通話中に幼児退行して泣き出したり、違う人格になって泣き出す人などがいた。自我の機能不全が激しいと、匂いなどのトリガーがなくてもランダム的もしくは特定の話題がトリガーになってフラッシュバックが起こり、それに伴って別の人格に切り替わったりしても不思議ではない。フィクション作品への入り込み方も常人の比ではないだろう。
他のフィルターの例えとしては、俺が2019年10月に幻覚剤を使用してトリップした時、あらゆる感覚が鋭敏になったのを覚えている。それはいろんな点で、普段張り付いていたフィルターや膜のようなものが取り払われたような体感だった。視覚は鏡で自分の表情を見ると顔の皮膚が動く一瞬一瞬が認識できたり、外で耳を澄ますと普段聞こえないような遠くのほうの音が聞こえた。ビジュアルスノウという視覚の病気は今も続いているが、これは視界に必要な薄皮が一枚剥がれたようなものという印象を受ける。

自我のフィルター機能が薄ければ薄いほど生きづらくなるのは間違いない。人格交代や幼児退行は人間関係に支障をきたすし、音が鋭敏に聞こえすぎると都会の喧騒にも耐えられないだろう。フィクションの作品の世界観を引きずるだとかも日常の中でいちいち起こっていたら勉学や労働などに集中しづらくなる。俺が20歳代後半まで週40時間の労働ができなかったのもそういった自我の影響があったように思う。
以上が俺が思う自我の機能の2つ目で、世界観に関する仮説としては、自我のフィルター機能が弱いことで外界が持つ世界観をダイレクトに受け取って奥まで入り込みやすく、潜在意識と顕在意識の境界線が薄いことで潜在意識に保存されている記憶が持つ世界観がフラッシュバックしやすくなる、という感じだ。それがおそらく夢の中にしか存在しない世界観を感じることにもつながる。また1つ目の機能と2つ目の機能は両方とも必要不可欠な自我の機能なので、1つ目の『自我の構成が世界観を作る』という仮説と2つ目の仮説のどちらが正しいというより、どちらも合わさって世界観が作られているのだと思う。
以上のことを踏まえた上で、本題である夢の中にしか存在しない世界観について説明する。
夢の中にしか存在しない世界観の特徴
夢の中にしか存在しない世界観(長いので以下から夢の世界観と呼ぶ)とは文字通り、現実世界のどんな場所に行ったとしても感じられない、もしくはフィクションの作品ですらほぼ感じられない、夢の中でしか・夢を見ているときしか感じられない世界観・雰囲気のことだ。上述の世界観の話に納得できるという人はおそらく夢の世界観についても心当たりがあるだろうが、ピンと来ない人のために夢の世界観の特徴をできる限り説明しようと思う。世界観とは感覚でありそもそも言語化できないものだと書いたが、AIが作成した小説には夢の世界観がある(後述)ので、おそらく俺も表現力次第では読み手にある程度想起させることができるかもしれない。もちろん画像もいくつか載せる。
まず、ネットで夢の世界観について語っている人をいくつか見つけたので引用する。
夢の世界の雰囲気や空気感ってなんか気持ち悪くないですか?
悪い夢を見た時に限らず、現実世界にはない独特の不気味な空気が常に夢の世界に漂っていて不快です。
とても言葉で言い表しづらいですが。だから夢から覚めて間もない時間は、現実に戻ったのに夢の世界の空気感が未だ残っている感覚があり、少しの間は気分が悪い時があります。
この感覚わかる方いますか?
夢を見て起きたらなんとなく部屋の雰囲気が違うことってありませんか?
楽しい夢や怖い夢、不思議な夢とか・・うまく言えないのですがたまに夢を見て朝起きたとき、いつもの家じゃないような雰囲気の
時ってないですか?
家具の配置とか一切何も変わっていないのですが、久しぶりの旅行から帰ってきたような・・
たいていは学校や仕事に行く頃には元に戻っているのですが、これって何なんだろうな~と・・。
一人目は夢の世界の雰囲気のことを気持ち悪いと言っていて、二人目もどこか奇妙そうに思っているようだ。また二人とも俺の上述の世界観の説明とかなり似た表現をしている。彼らが感じた夢の世界観と俺が言っている夢の世界観が同じものかを完全に立証する方法はないが、おそらく近いんじゃないだろうか。俺が思う夢の世界観の特徴を以下に羅列する。
・宇宙空間や他の惑星の印象がある。
・ポストアポカリプス的な街並みや、自分しか人間がいなくなった地球のイメージに近い。
・多くの場合人混みは出てこない。自分しかいないか、いても2人か3人。
・現実での馴染み深い場所を改変した場所が多いが、雰囲気は全く異なっている。
・基本的に感情がない。歓喜、激怒、号泣、性的興奮など大きな感情の動きがない。不気味さや冷たいイメージはある。
・悪夢とハッピーな夢なら前者のほうが多いが、基本的にどちらでもない場合が多い。
上から順に説明するが、まず上2つは俺が感じてきた夢の世界観に最も近い例えだ。これまでゲーム、映画、アニメ、小説などそこそこいろんなフィクション作品に触れてきたが、そのどれに出てきた場所も夢の世界観と同じだと呼べるものはなかった。Google Earthなどを使えば色々な世界の絶景を見られ、中には非現実的なほど美しいものもあるが俺が言う夢の世界観を感じられるものはほとんどない。強いていうならウユニ塩湖は近いが、やはりどこか違うので画像は貼らないでおく。俺が思う夢の世界観を感じられるのは主に宇宙空間や他の惑星のような場所で、以下の画像は夢の世界観にかなり近い。

画像参照元:Download Ai Generated, Planets, Night Sky. Royalty-Free Stock Illustration Image – Pixabay

画像参照元:Download Ai Generated, Planets, Stars. Royalty-Free Stock Illustration Image – Pixabay
またはポストアポカリプス的な街並みだ。ポストアポカリプスとは終末ものとも言われ、核戦争などが起こって人類が滅びかけて極端に数が減り街などが荒廃した世界観のことを言う。フィクション作品で言うならThe last of usがポストアポカリプスの代表的な作品で、ゲーム内でも俺が言う夢の世界観を感じられる場面がある。以下は夢の世界観を感じるポストアポカリプス的な画像だ。
ポストアポカリプスも宇宙空間も人が少ないか居ないような場所だが、夢に出てくる場所も極端に人が少ない。人混みだが夢の世界観がある、という場合もあるが珍しく、基本的にパーティやライブ会場など大勢の人がいたり熱狂している場というのは夢の世界観と相性が悪い気がする。ポストアポカリプスはディストピアと似ていると言われるが、俺はディストピアからは夢の世界観はほとんど感じない。ディストピアの世界は治安が極端に悪いが人類や文明は普通に存続していて、ポストアポカリプスの世界は人間や文明の数自体が少ないのが特徴だ。人の数は夢の世界観と関係が大きいように思う。例えば今現在の地球でも、自分以外の生き物がすべて消えたことを想像・想定してみると少し夢の世界観を感じる。
夢の中に出てくる場所についてだが、これまでいろんな場所が出てきた。夢に出てくるのはほとんどは夢オリジナルの場所だが、現実にある馴染み深い場所が出てくる場合もある。しかしその場合も現実でのその場所の雰囲気はほぼ感じられず、夢の世界観で覆われている。宇宙空間やポストアポカリプス的世界はわかりやすく夢の世界観を持っているというだけであって、例えば普通の日本の街並みでも夢に出てきた場合は夢の世界観を持っている場合が多い。現実の場所が出てくる場合多くは改変されていて、ある場所から先はいきなり夢オリジナルの世界が広がっているということがほとんどだった。俺はこれまで夢に出てきた場所をいくつかメモってあるが、それらの場所同士が物理的に地続きであるのかはわからない(そもそも夢なので『物理的に』という表現自体がおかしいかもしれない)。夢に出てくるすべての場所に共通しているのは夢の世界観を持っているということだけだ。
夢の世界観と感情
夢の世界観を感じる夢を見ているときは感情に大きな動きがない場合がほとんどで、漠然と不気味さを感じているだけの場合が多い。夢の世界観というのはとにかく「しん」としている。ハッピーな夢だったり悪夢だったり、感情が動く夢の場合は夢の世界観は弱まる傾向がある。激怒、号泣、性的興奮など大きな感情の動きは、夢の世界観と相性が悪い気がする。
『夢の世界観を感じない夢』を見ることもある。逆に言えばそういう夢は怒りや幸福感など感情の動きが大きい。夢の世界観の感じたことがないという人は、夢の世界観を感じない夢ばかり見ているのかもしれない。俺は上述の幻覚剤体験時に飲み合わせなどを間違えて事故って今に至るまで後遺症が残っているのだが、明らかにその頃から夢の世界観を強く感じ始めたり、またはそれを感じる夢を頻繁に見るようになった。『現実とほとんど変わらない世界でハッピーな夢または悪夢を見る』ということはほとんどなくなった。

以上が俺が感じている夢の世界観のできる限りの説明だが「夢の中にしか存在しない世界観と聞いてピンときたけど、その文章や画像からは私が感じている夢の世界観は感じられない」という人もいると思う。万人が共通の夢の世界観を感じているかは謎だ。そもそも現実の世界観であっても他人がどんな世界観を感じているかはどうやってもわからない。同じ場所にいて同じ景色を見ていても感じている世界観は違うかもしれない。独我論とか哲学的ゾンビの話だ。例えば『引っ越して日が浅い日に感じるその場所の雰囲気』が住んでいるうちに失われてしまうという経験をしたことがあるが、初めて人を家に招いた時なども相手が感じている世界観は自分が感じているものとは違うのだろうと考えたりする。
俺の場合だが、上述のように人生の各時期ごとの雰囲気で同じものは一つもないのに、夢の中にしか存在しない世界観は小さい頃から今まで変わらない。子供の頃に感じた夢の世界観と昨晩見た夢の世界観はほぼ同じで、それも不思議だ。俺が言う夢の世界観とは、俺という自我、魂、脳だから感じられる世界観であって、万人共通のものではないという可能性もある。その人が感じた夢の世界観を文章や絵や映像で表現して、俺がそれらに触れて同じ世界観を感じたら、その人が俺と同じ世界観を感じている証拠としてもいいかもしれない。
以下では夢の世界観を起きたあとも引きずる現象について書いていく。
起きて少しの間夢の世界観を引きずる現象
上記のYahoo知恵袋の質問者は二人とも、起きて少しの間はその世界観を感じ続けている・引きずっているということを言っているが、これは俺もまさに経験があり、上述した映画ロスの話にも近い。10代の頃はよくあったが、年を取るごとに自我の機能が強まっていったのか減っていった。ちなみに夢の世界観を現実でも少しでも長く感じるには、目が覚めてもすぐにスマホを見たりせず、再度その夢を思い出すと良い。夢の世界観は現実で何らかの刺激が入ると消えやすい。
スピッツの正夢という曲の歌詞に『今朝の夢の残り抱いて』という一節があるが、おそらくこの歌詞はこの現象を表現している。俺は中学くらいからスピッツのファンだが、草野さんは頭の中で5つくらいの架空のストーリーが同時進行していて、それが曲のアイデアになったりしているとなにかで読んだことがある。彼の繊細さと天才的な感受性なら、上述の自我のフィルターの話や世界観のフラッシュバックの話もあてはまるのではないかと思う。そもそもミュージシャンや画家や作家は多かれ少なかれそういった感性を持っているはずだ。ちなみにスピッツの曲の中だと『水色の街』は少し夢の世界観を感じる。
上述の『夢の世界観を感じない夢』を見た場合でも、例えば中学生時代に戻ったような夢だった場合、起きて数分間だけ世界の見え方が中学時代の自分に戻ったような感覚があった。その状態になると上述の匂いによるフラッシュバックと同じで、中学時代の自我と今の自我を比較してこんなにも変わったのかと感じたりする。今と昔で自分がほとんど別人のように感じられ、自我に連続性があるという当たり前の感覚自体が錯覚なのではないかとさえ感じる。この現象も年を取るごとになくなってきて、幻覚剤事故以降はほぼない。
俺は数年前それらの現象がどうしても気になり、知り合い10人くらいに一斉に「見た夢の雰囲気を起きて少しの間引きずったような経験はあるか。過去の自分に戻った夢を見た場合、起きて数分間過去の自分の戻ったような世界の見え方になったことがあるか」という質問したことがあるが、はいと答えた人はいなかった。やはりこういった体験をする人は少数派のようだ。似たエピソードだと、幻覚剤事故から約1ヶ月後の昼に名古屋のプライム赤池という場所に行ったのだが、日差しと風が気持ちいい中、数十分間世界の感じ方が17歳の頃としか思えない状態になり混乱した。例によって今の自我と対比し、こんなに変わってしまったのかと愕然としたのを覚えている。
また、俺は幻覚剤事故半年間くらい離人症や不安感に悩まされていたが、その間、映画や作品の世界観を数日間も引きずるということがあった。例えばコロナの影響で俺の好きな『君の名は。』が再上映されていて数年ぶりに見たのだが、見終わってから5日間くらい現実での生活が常に君の名は。の世界観に覆われたままで怖かったのを覚えている。当時スーパーのレジで働いていたが、レジから見える街の景色が現実のものとは思えず、そこからフィクション世界が広がっていると感じることを止められなかった。これは小学生のときの映画ロスやゲームロスの比ではなかったので、薬物は恐ろしい。
以下ではこの記事のタイトルにもなっているAI生成画像と夢の世界観の関係について書いていく。
AI生成画像の世界観
近年AIが台頭してきて、人物・背景問わず画像を生成できるようになった。俺は数年前初めてAI生成の背景を見たときから「AI生成の背景画像は俺が思う夢の世界観を持っている」と感じている。上に貼った宇宙の画像はどちらもAI生成のものだが、AI生成の背景であれば宇宙やポストアポカリプスでなくても俺が思う夢の世界観を感じられる。繰り返しになるが「AI生成画像を見たときの感じは自分が夢を見ているときの感じと同じだ」と思う人は、俺と同じ夢の世界観を感じているはずだ。

画像参照元:Download Ai Generated, Planets, Night Sky. Royalty-Free Stock Illustration Image – Pixabay

画像参照元:Qyraxos on X: "Path to the abyss. https://t.co/ZzVCQmx0eJ" / Twitter

画像参照元:Piotr Binkowski on X: "No mission. Just motion. https://t.co/7SJSFst85q" / Twitter

画像参照元:Cat sitting on ledge looking at city at sunset Generative AI | Premium AI-generated image
人物や動物などの生き物は例外で、それらに対して「夢の世界観にしか存在しない人物・動物だ」と感じることはない。また以下のAI生成の背景は人物(マリオ)が写っていることで、夢の世界観を感じる度合いは弱まる。やはり夢の世界観と人物は相性が悪い感じがする。
なぜAIが生成した背景画像から夢の世界観を感じるかに関して、線や色や光源など表面的な分析よりも画像生成の仕組みについて考えるのが重要ではないかと思う。AIは膨大な数の画像データを学習してそのバックボーンの上で画像を出力しているはずなので、AI生成画像は様々な人が描いた絵や現実世界の様々な場所(の写真)が持つ世界観の『平均値』となるんじゃないだろうか。絵からは描き手の自我や世界観がにじみ出るものだとすると、AI生成の絵は人類の自我の平均ということになる。人類の自我の平均や現実世界の場所が持つ雰囲気の平均、それが夢の世界観の正体の一つではないかと俺は考えている(後述)。
人間が描いた絵はどうしてもその人の自我や世界観が反映されてしまうので、夢の世界観を描くのは難しいと思うがいないことはない。俺はpixivでだいぶ前から活動している『名前のない絵師』という人が描く絵は夢の世界観を持っていると初めて見たときから感じている。壮大なファンタジー背景を描く絵描きは結構いるが、俺が思う夢の世界観を感じる絵を描く人は少ない。
彼の作品を最初期から順に見ていくと最初は各作品に人物が数人出てくるのだが、次第に不穏な空気になっていき、ある段階から人物は出てこなくなり背景だけの絵しか投稿しなくなっている。彼は作品すべてがストーリーになっているようだが、人目を引きたいなどの意図的なものではなく、頭の中でストーリーが勝手に進行しそれをただ忠実に描いているように見える。おそらく彼もスピッツの草野さんのように頭の中に世界・ストーリーがありそうだ。俺は昔からネット上のこういう浮世離れした人に興味を持つ傾向があり、彼の性別、年齢、どんな仕事・生活をしているかが気になるが、誰も知ることは出来ないだろう。
ちなみに俺も絵を描くが背景は全く描けないし、自分が感じた夢の世界観を絵で表現することは出来ない。夢の世界観のインプットはあるが、アウトプットに関しては別途絵の練習をしないといけない。俺が興味があるのはむしろちほ(俺オリキャラ)たちの自我丸出しの絵なので、今後も夢の世界観を題材にした背景絵などを描くことはないと思う。この記事のアイキャッチ用に夢の世界観を表現した絵を自分で描ければよかったが描けないので仕方なくフリーのAI生成画像にした。
AIが生成するものは背景画像だけでなく物語でも夢の世界観を感じることがある。たまにChat GPTにちほとあきら(俺のオリキャラ)の長めのファンタジー小説を書いてもらうが、読んでいて感じる世界観は俺が思う夢の世界観であることが多い。Grokに神秘的で情景描写多めの短い話を書いてくれと頼んで出力された文章も、読み進めているうちに夢の世界観を少し感じた。
具体的にどのワードや展開の仕方が重要かなどの細かい理由はわからない。読み進めているうちに全体として夢の世界観を感じるとしか言いようがない。これもやはりAIがディープラーニングによって人類が書いてきた様々な文章をインプットし、人類の自我の平均のようなものをアウトプットするようになっているからじゃないだろうか。気になる人はChat GPTやGrokなどに小説を何個か書いてもらって読んでみてどう感じるか試してほしい。情景描写多めと指定するのをおすすめする。
AI生成のコンテンツは問題になってるが、俺としてもやはり世の中がAI生成のコンテンツだらけになるのは気味が悪い。起きながらにして夢の世界観を感じる(後述)機会が増えるからだ。
AI生成の音楽についてはなぜか夢の世界観を感じることは少ない。俺の好きなLo-fi chill popなどはAI生成のものがYoutubeで出回っているが、夢の世界観はあまり感じない。ちなみに実際のミュージシャンが作った曲でも夢の中にしかない世界観を感じる曲はゼロに等しい。強いていうなら俺が中学の頃から好きなSyrup16gというバンドの『翌日 (Original Ver.)』という曲の冒頭なのだが、これはボーカルの五十嵐隆ソロの生還というライブDVDにしか収録されていないのでここに貼ることはできない。興味がある人は買って聴いてみてほしい。また同バンドの『回送』という曲も、夢の中のことを歌っている曲の中では比較的夢の世界観を感じるが、かなり強烈にというわけではない(なのでここには貼らない)。自分にとって夢の世界観を感じるという画像や音楽があればTwitterのDMなどで送ってくれると嬉しい。
寝ているときに自我は崩壊している
夢という現象は長年研究されていて、例えば夢は人間が他の世界と接触するための道であると信じられていたり、夢に出てくる生命は別の現実に実際に存在するものだと言われていたり、オーストラリアのアボリジニは、夢こそがむしろ「本当の世界」であり、夢とはその世界と交信する手段だと考えているらしい。他にも過去世やデジャブなど、夢とは何なのかについては古今東西で様々な仮説があってきりがないので割愛するが、俺が一つ確信しているのは『人間は寝ている時に、多かれ少なかれ必ず自我が崩壊している』ということだ。
自我が崩壊している状態とは上述の『自我の機能』が弱くなっているか、働かなくなっているということだ。例えば自我の構成は一時的に崩壊し、フィルター機能は弱まって顕在意識と潜在意識の境界線は曖昧になり、過去の記憶がランダムにフラッシュバックしたりしている状態だ。つまり夢を見ているときはみんな統合失調症的であり、解離性障害的であり、幻覚剤をやっているような状態ということになる。だから夢の中では現実ではありえない支離滅裂なことが起こる。夢を記憶の整理・デフラグだと捉える説があるが、電化製品を掃除する時のように、自我が機能している状態(電源ON状態)ではなく機能していない状態(電源OFF状態)じゃないと整理がしづらいのかもしれない。
そして、自我が崩壊しているというのは夢の世界観を感じる前提条件だとも思う。夢の世界観とは何なのか、睡眠時の自我崩壊などを踏まえて俺は基本的に以下の二つの仮説を考えている。
仮説1:この世界の本来の世界観
1つ目の夢の世界観の正体に関する仮説は『誰しも夢を見ているときに自我が崩壊しているなら、夢の世界観はこの世界の本来の世界観ではないか』というものだ。
自我の機能とは、この世界に自分が自分という一個人としてちゃんと存在するための機能だと書いた。それが崩壊するということは、世界及び他者との境界線がなくなり、融合する・溶け合ってしまうということだ。自我が崩壊するということは、自分の好みや価値観など自我による色眼鏡がなくなり、ありのままの世界を見れるということだと言えないだろうか。夢を見ているときは自我が崩壊していると仮定すると、夢の世界観こそが『この世界の本来の世界観』ということになる。
普段現実世界で起きて活動しているときは自我がしっかりと機能していて、それ故に良くも悪くもあらゆる物事が自分の価値観や好みのフィルターを通してしか見れない。また人それぞれ自我の構成・優先順位が千差万別なので、現実世界の場所や人や物や作品はこれだけ多種多様な世界観があるのではないか。現実で感じられる世界観は人の数・自我の数だけあり、つまりそれぞれが自分の自我というフィルター・膜を通じて世界を見て、それぞれの世界観を感じているが、夢の世界観は自我の膜を取り払われたこの世界の本来の、生の世界観ではないか、ということだ。だとすると夢の世界観は万人に共通で、唯一ということになる。
この仮説はスピリチュアルでよく言われるワンネスや、インド哲学で言うところのブラフマンやアートマンなどとも少し通じる。ワンネスとはすべての存在は精神世界及びソースエネルギーという場所でつながっていて、もともとは(今現在も)すべては一つだということらしい。ブラフマンとアートマンとは、個人の自我(アートマン)と万物の根源及び宇宙の根本原理(ブラフマン)は同一であるという考えだ。
ただこの仮説も納得いかない点があり、自我崩壊した人がみんな同じ世界感を感じるなら、すべての人間が例えばこの記事で表現した夢の世界観の説明に共感するはずで、また幻覚剤体験や臨死体験などで自我崩壊した人はみんな同じ世界観を感じていなければならないということになるが、実際はどうだろうか。
夢の世界観が万人共通ではないとすると『自我崩壊には度合いがある』という可能性が考えられる。例えば『夢の世界観を感じない夢』しか見ない人は、寝ているときも自我の崩壊度合いが弱いのかもしれない。逆に幻覚剤の高用量の服用や臨死体験で強烈に自我崩壊した人は、俺が言う夢の世界観よりさらに奥の世界観を感じていて、俺はその深度までは感じたことがないだけかもしれない。だとするとこの記事で表現した夢の世界観はあくまで俺の自我崩壊度合いで感じられる世界観なのではないか、という結論になる。
仮説2:個人的な記憶の平均
もう一つの夢の世界観の正体の仮説は、AI生成背景が夢の世界観を持っていることから導き出した『夢の世界観は、自分自身の記憶をディープラーニングした、個人的な記憶の平均値ではないか』というものだ。
人生の各時期にはそれぞれ特有の世界観があると書いた。当たり前だが人はこれまで現実で行った場所やフィクションの作品も含め、数え切れないほどの世界観を感じてきたはずだ。忘れてしまったもの、思い出せないものが大半かもしれないが、潜在意識には一つ残らず貯蔵されているという考え方がある。だとするなら、人は寝ているときに脳がAIの画像生成・映像生成の役割を果たして、これまでの記憶をランダムもしくは何らかの重要度に応じて混ぜ合わせているのではないか。それで出力された個人的な記憶・世界観の平均値が、俺が言う夢の世界観なのではないか。
『異なる世界観を混ぜ合わせる』というのは起きているときにはほぼできない。今、全く関係のない記憶・世界観を交互に思い出すなどして混ぜ合わせることができるだろうか。俺はそういったことを何度も試したことがあるができなかった。例えば小6のときの夏のプールの雰囲気と、25歳の冬の寂しい感じを交互に思い出したり、前者の世界の中に後者の世界の絵を入れ込むなどして混ぜ合わせようとしてもうまくいかない。あくまでも交互になってしまい、融合させた一つの世界観というのを感じることは出来ない。夢を見ているときは自我が崩壊しているから、そのような混ぜ合わせがうまくいくのかもしれない。
俺が言う夢の世界観が個人(俺)の記憶の平均だとしても、俺はAI生成の画像・文章という人類の平均であるものに対しても同じ雰囲気を感じる。『個人の記憶も人類の記憶も平均を出せば大体同じ雰囲気になる』ということなら個人的かどうかは関係なくなり、誰しも俺が言う夢の世界観を感じている可能性が出てくる。仮説1『この世界の本来の世界観』と仮説2『この世界の平均値』がどう違うかは説明できないが、同じものを指している可能性もあるかもしれない。
以上が夢の中にしか存在しない世界観の説明やサンプルと、その正体に関する俺の仮説となるが、結局のところ確信できる結論は出ていない。シミュレーション仮説や死後の世界と合わせて考えると他の視点を得られそうではある(後述)。
次に『起きながら夢の世界観を感じる』ということに関して書いていく。
起きながら夢の中にしか存在しない世界観を感じる
夢の中にしか存在しない世界観は基本的に寝ている時・夢を見ているときにしか感じられないが、何らかの方法を使えば起きながらにして感じることができる。俺も実際に起きながらにして夢の世界観を感じたことが数回ある。
2023年の暮れくらいに、強烈な夢を見て起きて目を開けると、自分の部屋を眺めているのに普段感じている自分の部屋の雰囲気ではなく夢の世界観が感じられた。気持ちいい感じがしたが少し怖かった。起きているのに夢の世界観を感じているというのは、起きているのに自我が正常に機能していないということであり、統合失調症や解離性障害になったようなものだからだ。
解離性障害と離人症
俺は解離性障害にも長年興味を持ってきた。それ故かこれまで累計4人の解離性障害の人と出会ってきたが、みんな性格も症状も似ていた。解離性障害と俺は相性が悪く、結局4人とも縁は切れた。
解離性障害とは主に幼少期のトラウマなどによって、辛いことから心を守るために意識が現実から解離したり、自己認識や記憶が分離する精神障害だ。解離が起こっている時、声を出して喋っているつもりでも現実では無言のまま、ということがあるようだ。また自分が常に何者から見つめられている感覚があり、統合失調症と区別するのが難しい場合も多いらしい。解離性同一性障害は俗に言う多重人格で、解離性障害とメカニズムは近く、人格の数が多い版という感じだろう。
解離性障害は自我の障害ということらしいが、解離している間にどのような世界観を感じているのだろうか。解離している間自我が崩壊しているなら、起きながらにして夢の世界観を感じていることはないだろうか。俺は幻覚剤をやったときでさえ現実から意識が解離したり記憶が分離したことはないが、幻覚剤直後から半年間離人症には悩まされた。離人症は軽い自我崩壊という感じがしたし、起きながらにして夢の世界観をわずかに感じていた気もする。君の名は。の世界観を引きずったのも離人症や自我の不安定さの影響が大きいだろう。
俺が出会った解離性障害の人の一人は「0歳の頃の記憶がある」と言っていた。赤ん坊の頃は無力な状態故に恐怖そのものの記憶になっていて、思い出すと発狂するため多くの人は思い出せないよう潜在意識の奥深くに封印されているという。解離性障害の人は自我のフィルターや潜在意識と顕在意識の境界線が薄いためそれらを思い出せるのではないだろうか。上述の通話中に幼児退行したり違う人格になって泣き出した人たちも記憶とその制御に問題があるように思える。
解離性障害の8割が女性というのも興味深い。男性に比べて女性の人格・自我はどこか地に足がついておらず、つらいことがあった時に現実で問題を解決する方向には向かわず向精神薬などをオーバードーズして気を失って現実から逃げようとする・自我を崩壊させようとする印象がある。解離性障害の人は向精神薬や幻覚剤などを使わずとも自力で自我崩壊を起こせると言えると思うが、それはある種の能力と呼べるんじゃないだろうか。俺は中学のとき現実から逃げるため明晰夢や体外離脱の練習をしたが、自我崩壊させるのが下手だったのか数回しか成功せず、幻覚を見る練習に関しては一度も成功しなかった。性別と自我の機能は関係が深い気がする。
解離性障害の原因の一つとして霊障説のようなものを考えたことがある。風邪やインフルのウィルスはそこら中に存在していて人の免疫力が下がるとそれらが体内に入り込んで増殖するが、霊もそこら中に漂っていて、虐待やトラウマや薬物で精神の力・自我の機能が弱るとそれらが精神に入り込んでくるということはないか、というものだ。もしそういったことがあるとすると自我の機能は精神的・霊的な免疫力とも呼べるんじゃないだろうか。また稀に悪魔憑きのような解離性障害の人がいて、その人の中の人格の一つは主人格とは別の国の言語を完璧に喋ると本で読んだ。これが本当なら人間の体はただの容れ物であり、多くの人は一身体一人格(霊)だが、解離性障害の人は複数の人格(霊)を入れられるようになっている、というようなことが考えられないだろうか。
以上のように解離性障害について色々と考えてきたが、彼女らは「理解されたいけど、踏み込まれたくない」というような二律背反を抱えている場合が多く、興味本位で近寄ると気分を害させてしまうので今後は関わらないつもりだ。
解離性障害に興味がある人は柴山雅俊氏の『解離性障害「うしろに誰かいる」の精神病理』という本を読むことをおすすめする。解離性障害の人が感じる視線の正体が自分自身の自我だった、ということなどが書かれている。夢の世界観に通底しそうなことも書いてあったので、この記事を読んでいる人はこの本も読んで損はないと思う。
幻覚剤と死ぬ直前の世界観
起きながらにして自我崩壊させ、夢の世界観を感じる第一の選択肢は幻覚剤だろう。幻覚剤と呼ばれる類の薬物は自我展開剤と呼ぶ人もいて、自我を崩壊させることで潜在意識のトラウマを取り出して向き合い解消したり、人生の真の目的に気づくことができると言われている。結論から言うと、取り返しのつかない大変なことになる可能性が高いので絶対におすすめしない。現に俺も事故を起こしたとはいえ死ぬかと思うような経験をし、5年経った今でもビジュアルスノウ、フラッシュバックなどの一生治らない後遺症が残っている。
幻覚剤は『自我のフィルター機能が分厚すぎる人』への荒療治としては使えるのではないかと思うことはある。自我のフィルターが薄いほど生きづらいと書いたが、逆に自我のフィルターが分厚いと他者に対して無神経になり生きやすそうだ。しかし共感性が欠如し、傍若無人になり、変化もしづらくなるのではないかと思う。その場合、幻覚剤によって自我を一旦バラバラに破壊するしか変化する方法はないのかもしれない。だが本来コツコツと時間をかけて変化させていくはずの自我の構成・価値観を一挙に変えると、かなり不安定なことになる。俺も幻覚剤で事故った直後「生まれ変わってしまった、これを境に第二の人生が始まった」という体感に包まれたが、自分が自分でないような恐ろしい感覚でもあった。最近の日本のでも、LSDを使用した女性が「新しい自分になる!」と叫んでマンションから飛び降りて死んだ事故があった。
強烈な幻覚……「新しい自分になる」と8階から飛び降り死 危険ドラッグ「1D-LSD」とは? お香に偽装も【#みんなのギモン】(2024年4月9日掲載)|日テレNEWS NNN
話が逸れたが、俺は幻覚剤のトリップ中は起きながらにして夢の世界感を感じたことはないと記憶している。ただ救急車で運ばれた日(2019年10月5日)の昼、近所のガストに昼食を食べに行った時『人生最後の日にしか感じられない世界観』としか形容しようのない世界観を感じて恐ろしかったのを覚えている。今日100%死ぬことが確約されてる実感というか、死後の世界が目前まで来ていて、現実が最後の極彩色を放ってるような感覚があった。人が死ぬ時にはみんな現実が最後の極彩色を放つ感覚を覚えるのかはわからない。結局その日に死ぬことはなかったが、少なくとも渦中にいる時は今日死ぬと思わざるを得ないような圧倒的な体感があった。あんな恐怖は二度とごめんだ。
俺の幻覚剤事故前後に閉鎖した旧ブログ『髭林ダイナマイトスタジオ』には『脳内世界と夢の中にしか存在しない世界観』や『宇宙の本質はノイズである』というようなタイトルの記事があった。ローカルからも削除してしまったので確認はできないが「この宇宙の本来の姿は~」とか「夢の世界こそ本当の現実だ」とか書いていた。結局それから数年後に、精神世界を探求するなどと言って本当に幻覚剤をやってしまった。今この記事を読んでいる人や明晰夢や体外離脱などに興味を持っている人は、幻覚剤にも少し興味があるんじゃないだろうか。何度も書くが絶対におすすめしない。幻覚剤で悟った気になり、ネットで体験談を書いていたずらに人の好奇心を煽るのが関の山だ。「すごいやつ・わかってるやつだと思われたい」という気持ちでやってもろくな結果にならず、後遺症や自我障害で後悔することになるだろう。
Daydreamさんについて
2020年、俺が幻覚剤後遺症のTwitterで幻覚剤後遺症の人を探しているときに知り合ったDaydreamさんという男性がいる。彼とはDMでいくらかやりとりし、2回ほど通話もした。この項目では夢の中にしか存在しない世界観というより引き続き薬物の危険性について書きたい。
彼は20代前半で、これまでインドなどを旅してリキッドタイプのLSDなどを何度かやってきたそうだが、DMTのような強烈なトリップはなかったそうだ。日本に戻り、就職前に合法紙を通常の1/8やってトリップの覚める前に深酒をしてから、前頭前野機能障害的症状+ビジュアルスノウになったらしい。
LSDで脳が焼かれ、廃人間近の23歳無職です。以前は綺麗な景色や感動を求めて旅をするのが好きでした。
Lでおかしくなるのは、かなり少数派だと思います。同じ状況の方等いらしたら、情報交換しましょう!#薬物後遺症#薬物#HPPD— Daydream (@r0UtPEGeT3lUgKb) June 18, 2021
私は大学を卒業し、そこそこいい会社にも就職し、人生これから!という時に薬物で脳がイカれました。
具体的な症状は、著しい思考力の低下、無感情、飛蚊症、ビジュアルスノウ等。
サイケデリクスは合う人はとことんやっても大丈夫ですが、合わない人は本当にイカれてしまいます。#薬物後遺症— Daydream (@r0UtPEGeT3lUgKb) June 18, 2021
幻覚剤の後遺症。
誰にも言えず、単なる精神障害者として振る舞うしかない。
治療法も多分ありません。— Daydream (@r0UtPEGeT3lUgKb) June 19, 2021
空を見られない
— Daydream (@r0UtPEGeT3lUgKb) June 20, 2021
この4つのツイートがすべてで、「空を見られない」というのが最後のツイートとなる。
彼とのDMのログは残っていないが、以下のメッセージだけは残っていたのでそのまま引用する。
前頭葉が細胞レベルで破壊された様な感覚ですね。私の場合、思考が全くありません。常に頭の中に波風立たずって感じです。故に感情も薄いんですよね。正直海外のサイトを見ても自分はかなり重症のようです(苦笑)
以前の自分を100としたら今の自分は10にも満たない感じですね。
「一生このままかも知れない」という考えはふと出て来ますが、実感として心から感じることは無いですね。「ふーんそうなんだ」くらいの感覚です。感じようと思ってもなにも感じません。
通話してみると普通の好青年で、本当にそんな深刻な状態なのかと思ったが、演技していたとのことらしい。演技しなければという命令はどこから来るのかなど疑問は残るが、わからないままだ。彼はその年の夏に「薬物後遺症に詳しい医者を尋ねる」と言ったきり連絡がつかなくなった。
彼は
『常に醒めていて、すべてを悟ったような感覚が永続している』
『何をしても、壁をぼーっと見ているときと同じ感覚』
という状態らしく、ゆえに死ぬのも怖くないと言っていた。彼は薬物の事故以降、起きながらにしてずっと夢の中にしか存在しない世界観を感じていたのかもしれない。上述の、夢の世界観には大きな感情の動きがないという特徴にも当てはまる。
俺も一時Daydreamさんと同じ状態になったので、永続しなくて本当によかったと思う。幻覚剤事故の3日後、甲状腺の病気になったと勘違いして名古屋甲状腺内科を受信し、待ち時間に近くの公園をうろついていた時、明鏡止水のような状態になり「すべて悟った、この世のすべてがわかった」という精神状態になった。確かに心に一切の波風が立たず、恐ろしいことを考えても恐怖が湧いてこなかった。しかし夢の世界感はほとんど感じず、現実の世界感だった。数時間で元の状態に戻り、事故後のひどい不安感が戻ってきた。
DaydreamさんのようにLSD、紙、アカシア茶、合成カンナビノイドなどを使用して感情がなくなり、単純作業もできないほど集中力もなくなり、常に離人症的で自分を遠くから見てるような状態が永続してしまっている人は絶対に他にもいるはずだ。そういった薬物を使って事故った人は大きな声で発信することが難しいため、見つけにくい傾向がある。俺の幻覚剤後遺症も5年経ってやっと発信する気が起きた。今幻覚剤に興味がある人は取り返しのつかないことになる前に考え直したほうがいいと俺は思う。
メンヘラポエムの世界観
昔から、メンヘラと呼ばれる女性たちは独特なポエムを書くと言われている。俺は彼女たちが書く詩の世界はなぜかある程度共通しているように感じる。それらは必ず抽象的で、強いメッセージ性や主張はない。視覚情報としては水彩画のような淡い色合いで、強烈だったりビビッドな感じはない。真っ白い部屋、体の冷え、血液、鈍い痛みなどの要素が出てきがちで、色白でガリガリの美少女がバスタブに浸かって手首や陰部から血を流していて、ここがどこかも、何時間経ったかもわからず、痛みと冷えが体を貫いていて、というようなものが多い気がする。俺には女性特有の(?)痛みと冷えなどについては理解できないが、そういう詩を読むとなぜか夢の中にしか存在しない世界観が脳裏に浮かぶ。
なぜ俺はメンヘラ女性のポエムから夢の世界観を感じるのだろうか。それは多分女性は男性よりも自我の機能が弱く、それ故に夢の世界観を感じやすく、それが詩に反映されているからじゃないかと思う。解離性障害の項目にも書いたが、女性はつらいことがあったときに現実で対処・解決しようとせず、向精神薬をODして気絶しようとしたり現実から意識を解離させたり(解離性障害)してやり過ごそうとする傾向がある。ある女性いわく、つらいときには自分が誰なのかわからくなってしまいたい、自我から逃げたいと思うそうだ。そもそも女性は男性よりも自己認識(自分はどういう人間かという認識)が薄いという研究があり、認知症も女性の方が多い。女性の自我の機能の弱さは母性や自己犠牲にも関係しそうだが、本題から逸れるので割愛する。
彼女らの一部はserial experiments lainという作品を好むようだが、この作品は概要を読む限り集合的無意識がテーマになっているようで、夢とも関係しそうだ。アートワークを見ると俺が思う夢の世界観を少し感じるので、いずれレンタルして見てみるつもりだ。
その他
死後の世界
他に書く場所がないので、ここに俺が現時点で思っている死と死後の世界について書く。俺は夢の世界観がそのまま死後の世界ではないと思うが、関係は深いと思っている。現時点では死後の世界がどんなものか、どんな雰囲気なのかはわからない。夢の世界観よりもっと強烈な世界観を持っていそうだとは思う。幻覚剤で臨死体験をしたという友人は死は全く恐ろしいものではなかったと感じたそうだが、結局本当の死ではなかった以上、本当の死もそのような感じかは確信が持てないと言う。
俺は幻覚剤事故から1ヶ月後くらいの夜、漠然とした不安感に耐えながら眠ろうとして布団にいる時にいきなり『自分の次の思考が次々わかる』という状態になったことがある。意識が後頭部より少し上くらいにあり、意識が7割くらい集合的無意識のようなものになり、普段の自分の自我は3割くらいで、集合的無意識としての意識が他者を見るように自分の自我を眺めていて、次の瞬間何を考えるかが次々とわかるという感覚があり恐ろしかった。俺は死後の世界のことはわからないが、死に至るプロセスとして俺の自我・意識は宇宙の根源のようなものに溶けていき、自分を肉体や残りの自我を外側から眺め「今までこいつを演じてたのか」というような気分になるんじゃないだろうかと予想している。死とは『自分・この自我』とのお別れになるのだと思う。自我が溶けていく・崩壊していくと考えると、死への過程で夢の世界観を感じる可能性はかなり高い。
上述のインド哲学のブラフマンとアートマンの話は、ブラフマンが海でアートマンが波と例えられることがあるようだ。宇宙の根源(ブラフマン)は海で、一個人・それぞれ自我(アートマン)は波なので本質的に同じものだが、違うものだと勘違いすることが無知であり苦しみだという。
俺も宇宙の根源は海のようなもので、一個人の自我は海水を掬ったバケツのようなものではないかと思ったことがある。生きている間そのバケツに色々と海藻、貝、ゴミなどを入れて独自のものにするが、死ぬときにはバケツの中身をすべて海に返し、自分と他人の境界がなくなり、独自に組み合わせた海藻や貝(=自我の構成)が広大な海に混ざる。そしてまた誰かが生まれる時はバケツで海水を掬うが、その時に自分がかつて死んだときに海に返した海藻やビーズの組み合わせの一部が掬われたら、自分のかつての自我の欠片が誰かに転生したということで、自身の本質的な消滅はない、という話につながる。この考え方は、魂は一つであり何度も違う肉体で生まれ変わる、という考え方とは異なる。
またこの考え方は、一個人は葉っぱで死ぬときはその葉っぱが散るが、その木の根元に落ちてまたその葉っぱを構成する要素を土が吸収し、木の根っこが栄養を吸収しまた葉をつけるから、本質的には消滅していない、という話とほとんど同じだ。これはなにかの宗教の死生観らしいが俺は特定の宗教は信じていない。
そのような感じで俺の考え方は死後の世界や天国や地獄という考えではなく、自我が崩壊し宇宙の根源に還るのではないかと思っているが、いずれにしてもやはり実際に死ぬ以外に死を知る方法はないだろう。少なくとも俺は『死んだら全部無になる』とは全く思わない。海の例えであれ魂であれ、何らかの形で存在が続いていくことは間違いないと思っている。
シミュレーション仮説とバグ
最近リズワン・バーク氏の『われわれは仮想世界を生きている』というシミュレーション仮説の本を読んだ。ビデオゲームの歴史からAI、西洋・東洋の哲学・宗教、夢の世界まで満遍なく取り上げてシミュレーション仮説を説明していてかなり満足できる一冊だった。俺は小学生くらいから独我論、中学生くらいから水槽の脳や世界五分前仮説などについて考えていて、現在はシミュレーション仮説を信じている。夢の世界観こそが現実(このゲームの外側)であるという仮説も俺の中にあり、死とは単なるログアウトもしくはキャラデータの作り直しだと考えることもある。
この本には幻覚剤についてはほとんど書かれていなかったが、俺は幻覚剤の使用はゲームにおける裏技やバグ技のようなものだと思っている。例えば初代ポケモンではアイテム欄でセレクトボタンを何回か押すなどしてゲームを意図的にバグらせることでレアアイテムや伝説のポケモンを手に入れられるが、一歩間違うと『進行不能バグ』という致命的な状況に陥る。この世界がゲームだとすると、幻覚剤というバグ技を使って人生をどうこうしようとして重篤な障害が残ったりするのは進行不能バグと呼べるのではないか。俺が幻覚剤で事故ったことで患ったビジュアルスノウ、フラッシュバックなどの永続的な後遺症もバグと言える。進行不能バグにまでは至ってないのが救いだった。
どんなゲームでも、バグ技を使ったりチートなどの不正はするなというのが常識であり、何らかの代償やペナルティがつきものだ。やはり薬物はやるべきではない。
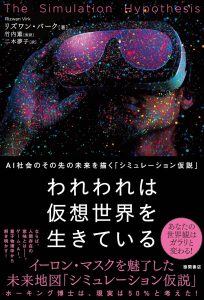
われわれは仮想世界を生きている AI社会のその先の未来を描く「シミュレーション仮説」
現実よりもリアルな夢と体外離脱
2019年10月の幻覚剤事故から今に至るまで後遺症が残っていて、5年経った今でも入眠時にフラッシュバックが起こることがある。上述のように夢の世界観がある夢を見る頻度も圧倒的に増えたし、脳が変性してしまったんだろう。この5年間で何度か現実よりもリアルな夢も見た。現実よりリアルというのは説明が難しいが、実際にそう体感したとしか言いようがない。
1回目は、自分の家の玄関を出ると実際の景色ではなくDMT worldのような世界が広がっているという夢。
2回目は、普通の夢の最後に、高層ビルのテラスから向かいの高層ビルにラシュモア山の胸像のようになったうさぎや動物のマスコットキャラクターを眺めていた。街中が動物のマスコットやパレードのカラフルな飾りつけや風船だらけでDMT的な鮮やかさがあった。
どちらも、AI生成の『DMT World』と呼ばれる画像の雰囲気そのものだった。普段のフラッシュバックはすべて灰色で強烈さはないが、それらの夢は極彩色で、遠くから見ているのに視界に入るものすべてが至近距離で見ているような圧倒的なダイナミックさがあった。
中学から高校の頃VIP(2ちゃんねるの板)で最近体外離脱にハマったというスレがあり、当時不登校で人生が辛かった俺は現実逃避のために明晰夢や体外離脱を実践していた。ロバート・モンローの『体外への旅』という本も買ったり、ヘミシンクという脳波を体外離脱しやすい状態にする音声を聴いて眠ったりしていた。
成功したのは累計10回未満で、体から幽体(?)が抜け出る感覚は確かにあったし、抜け出したあと体から離れようとすると体に引っ張られる感覚もあった。体外離脱で行ける世界は途中までは現実の自分の部屋だが、外に出て進んでみると現実の世界とは違うオリジナルの世界が続いていることがほとんどだった。DMT worldのような極彩色感はなかったが、現実よりリアルな体感はあった。明晰夢や体外離脱は成功しないことがほとんどだったし失敗すると時間の無駄になるので、リアルでの生活が楽しくなってきてからはそういったことに興じることはなくなった。
どちらも俺が言う夢の世界観が強烈にあり、こっちが本来の世界なんじゃないか、死んだら(肉体が滅んだら)こっちの世界に行くんじゃないか、という体感があったが、俺の脳の状態だからこそ見られる個人的な世界かもしれない。探求してもきりがないので今はそういった夢を意図的に見ようとは思わない。
まとめ
最後まで読んでくれてありがとう。この記事では夢にどんな生き物が登場するかやどんな展開が起こるかなどの、ユングやフロイトの夢占い的なことはほとんど書かなかった。どんな内容の夢であっても感じられる世界観は大体共通しているし、細かな内容よりも全体的な世界観のほうに興味があったからだ。
なぜ多くの人が夢の中にしか存在しない世界観に興味がないのか不思議だ。そもそも夢の世界観を感じる夢を見ていないか、もしそういう夢を見ていたとしても考えても意味がないと思い毎日スルーしているのだろうか。いずれにしても夢自体に興味がない人が多い。日々労働し、お金を稼ぎ、と現実世界で忙しくて夢のことなんか考えている暇はない、という感じだろうか。俺も10代の頃よりは夢の世界や架空の世界への興味が薄れたので、夢について考えるのが不毛だという人の考えもわかる。だがあまりに精神世界に興味がない人とは話が合わない。夢のことを考えるのは自分自身を見つめるきっかけにもなるし、完全に無駄とは思わない。要は現実世界とちゃんとバランスを取っていければいいんじゃないかと思う。
幻覚剤事故の前のブログ記事では、10代の頃の明晰夢や空想の世界を超える快楽がないとか、宇宙を漂う思念体になって悠久の時の中で地球の様子を観察したいとか書いていたが、今はそういう願望はない。俺は幻覚剤後遺症によるフラッシュバックがたまにあるので10代の頃より明晰夢や体外離脱の成功率は上がっているだろうが、もうそういったことに興じるモチベーションがない。俺の場合現実世界で行き詰まったときには啓示的な夢を見ることが多いので、そのときはその夢に向き合えばいいと思っている。
もちろん薬物も一生やるつもりはない。結局のところどれだけトリップしても死んでいない限りは戻ってくるのは現実世界であり、そこでやっていくしかない。俺にとってはそれが幻覚剤体験の答えであり、これ以上幻覚剤に求めるものはない。
俺は10代の頃人生がつらく母性に飢えていて、二次元キャラと夢で会おうとしたりしていた。その欲求はいろいろな経験を経て現実の恋人と、ちほというキャラに収束した。ちほやあきらなどのオリジナルのキャラを生み出せた今は、彼女たちの絵を描いて公開することのほうが夢の世界でキャラに会う快楽よりも大きい。夢の世界観についてはこの記事でできる限りのことを書けて満足した。夢の世界観の正体は死ぬときにわかるだろうし、それまでは現実で地に足をつけて生きながら、ちほの絵を描いていければそれでいい。
現実と離れたとこにいて こんなふうに触れ合えることもある
もう会えないって 嘆かないでね雪風 / スピッツ